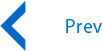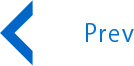Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/xs573794/focre.co.jp/public_html/admin/wp-content/themes/fc/single-column.php on line 4
31 評価項目ごとの「評価基準」はどのように設計すべきなのか?

評価項目や具体的な行動内容(プロセスや成果)は
比較的スムーズに決まることが多いです。
理由としては、
普段行っている業務を言語化するプロセスであるためです。
ただし、
「どの程度できたら5点なのか?3点なのか?」
という基準設定に悩むケースがあるかと思います。
評価基準は、
制度の納得感や運用のしやすさに直結するため、
設計方針が重要になります。
■評価項目ごとに評価基準を設けるとなぜ難しいのか?
一見、各評価項目に対して
細かい基準をつけた方が丁寧に思えますが、
実際の運用では評価者の負担が大きくなり、
継続性・整合性・比較性の担保が難しくなります。
特に少人数の会社や人事部門がない組織では、
項目ごとの基準設計・運用は非現実的です。
以前この方式で運用をしていましたが、
50名の組織では、現場実務・マネジメントなど色々とやることが多く、
その整合性を組織内で担保をするのは現実的に不可能でした。
■運用ファーストを考えると「コース×等級」ごとの基準設計がベター
評価基準は、
コース(例:Gコース・Sコース・Mコース)×等級で
設計するのが現実的です。
また、
等級要件書との連動性が重要になるため、
その部分に時間を使うほうが重要である
具体的な運用例(Gコース)がこちらになります。
Gコース
1点
・確認業務が必要とされる
・業務内容を理解できていないことがある
2点
・指示のもとで業務を実施できる
・業務内容をほぼ理解できている
3点
・単独で業務を実施できる
・業務内容を理解している
4点
・単独で高いレベルの業務を実施できる
・業務内容の理解度が高い
・他者に自主的に関わり、指導・アドバイスをしている
5点
・単独で非常に高いレベルの業務を実施できる
・業務内容の理解度が非常に高い
・他社の模範となっており、良い影響を与えている
評価シートの汎用性を保ちつつ、
等級に応じた期待値を基準でコントロールできます。
結果として、
評価者にも被評価者にも伝わりやすく、
育成にもつながる設計になります。
もちろん時間をかけられたらベストではありますが、
現実的には売上・利益を創ることが最優先になってしまうので、
時間をそこまで投下せずにできる運用体制が重要です。
評価制度の価値 =
成果につながる納得感 × 運用しやすさ ÷ 投下時間
を最大化できるようにしていきます。
①成果につながる納得感
基準が明確で、評価結果が成長や処遇に結びつく設計
②運用しやすさ
評価者・担当者がスムーズに使いこなせるシンプルな構成
③投下時間
設計・運用にかけられるリソース(≒実務に支障が出ない範囲)
実態として、
中小企業の役職者はやることが多く、
時間が取れない場合がほとんどです。
■評価基準のポイントは、 言語化&定義化が重要
各文言に定義を作っておくことが
非常に重要です。
人によって定義が違うため、
指導・指示といった言葉一つとっても
人によって捉え方が違います。
例えば人事コンサルティングの仕事を頼みたい場合、
「サービス名」が記載されていても
「サービス内容」が分からないケースがあります。
その場合、 「人事コンサルティング」のサービス内容が
社員によって解釈にずれ生じてしまい、
どこまでをサービスとして提供するかが
人によってバラバラになってしまいます。
そのため、
組織としての基準を明示しておく必要があります。
・どこかに書く必要がある
・その解説もすることでずれなくなる
評価基準自体も、
どのようになってほしいのか?
ということを示すための重要なところです。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
これは評価だけでなく、
事業・サービスも同様です。
①実はちゃんとした会話になっていないことが多い
②人によって言っていることが違う
などの問題が必ずと言っていいほど発生するので、
未然に防ぐためにも言語化&定義化を 忘れずに行いましょう。
最後までご覧いただいありがとうございました!