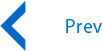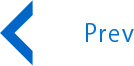28 評価は何のためにあるのか

これまでに評価の重要性をお伝えしてきましたが、
具体的にどのような評価シートで評価をすることが
良いのでしょうか?
評価シートは単に「評価」の点数を入れて終わりではなく、
当然ですが、組織のあるべき人材像、
そして組織の価値観をわかりやすく表したものです。
また、これまでと同様、
社員の行動が変化するために
振り返りを行うためのものでなければなりません。
あとは、できる限り「公平」であるシートを作る必要があります。
ただ、運用に耐えられるものでなければならないため
「最適解」を出す必要があります。
運用に耐えるとは、現行に合わせて運用できるレベルまでです。
結論としては職務は「職種」で
マネジメントなどは「コース」で括るといったイメージです。
■組織の価値観を言語化する評価シート
評価シートは「どんな人材を目指してほしいか」を形にするものです。
①「うちの会社らしさ」「大事にしている行動」を抽出する
Vision・Core Value・行動指針などに落とし込まれています。
②組織が大切にする考え方・行動基準を項目として盛り込む
行動指針・クレドなどをマインドスタンス評価として
いれるパターンが多いです。
③被評価者が「何を期待されているのか」を理解しやすくなる
具体的行動を記載する際に、
どういう行動を期待されているのかを
伝えることができます。
意図的に意識をつけさせるという意味でも効果的です。
④評価シートがあることで、フィードバックができるようになる
具体的に何を求めているのかが
明確になるためです。
■行動変容を生む振り返りの仕組み
①自己評価は当然マストである
まずは、自己評価を行ってもらいます。
自己評価自体、会社としての最終評価にはほぼ影響しませんが、
自分の立ち位置と会社が見ている立ち位置の差が見えるようになります。
また、ほとんど評価に差異がないことが理想的ですが、
評価がズレている場合には、
そのズレを解消するためのアクションが行えます。
会社の評価よりも、
従業員の自己評価がかなり上回ってしまっている場合、
自分自身をあまり客観視できていないと評価されてしまい
今後「役職者」にするのが難しくなります。
ズレがない=メタ認知ができていることにもつながるので、
被評価者は客観的視点を持って自己評価をし、
会社との評価のギャップを埋めることが重要になります。
②評価シートを活用して行動の振り返りを行う
これも当たり前ですが、次にどう行動するか、
成長に繋げる視点を明確にするために
評価で振り返りを行います。
評価結果を「納得感のあるフィードバック」に繋げる
導線をつくりましょう。
■公平性と運用性のバランスを考える
評価シートは究極的に言うと、
人ごとにカスタマイズされた評価シートが評価をしやすいですが、
それでは、公平でもなければ運用は不可能です。
そのためにも「コース」×「職種」×「等級」で
評価シートを構成することが必要になります。
コースはマネジメントの有無、
職種は、プロセス・スキルの違い、
等級は求める水準の高さのイメージで作ります。
指針をしっかり作成することができていれば、
「人」で見るのではなく、
コースごとや等級ごとの水準で公平性を持って
バランスよく運用していくことができます。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
①上司のフィードバックや被評価者への意識づけ
②自分の評価をメタ認知させ、会社の指標に近づけていく
③コースや等級ごとの水準で評価をし、公平性を保つ
の3点が重要な観点になります。
最後までご覧いただきありがとうございました!